第壱話 我んぬ浜に恵祥寺の鐘の音聞こゆる
|
若夏がなれば 蝶の羽衣に
ぬぎかえて心 すだくなゆき
|
時は一七世紀中頃、琉球はうりずんと呼ぶ初夏を迎え南風がそよいで心地よかった。 チルーは夕方の日差しが和らいだ頃合いに見計らって我んぬ浜(わんぬはま)へやって来た。その浜はチルーが勝手に自分の浜と名付けてお気に入りにしている秘密の場所だ。自分の身の丈の倍以上もあるほどの背丈の高いサトウキビ畑のあぜ道をぬけて鬱蒼と茂る藪や雑木の潅木の中に分け入ってゆくと道が獣道のように細くくびって曲がりくねっている。覆いかぶさった茂みが真っ暗なトンネル道を作っていた。程なくすると道は珊瑚の岩礁の浜久比里の道につながる。珊瑚砂を被った珊瑚の岩礁が細く狭い階段状になっていて段差はチルーの脛の高さ以上に高さがあった。大人の歩幅には容易であっても幼いチルーには結構難所だ。
 だがその難儀をかこってもチルーはその浜に下りることが嬉しくてたまらない。道をさえぎる葉や枝を小さな手で押しのけて分け入ってゆく。浜久比里の終点に白い珊瑚の浜辺が海鳴りを響ませて潮の香を滾らせてチルーを待ってくれている。横幅8間も無いであろう奥行きは2間弱だ。小さくて狭い場所だが子供のチルーにとっては天国のような開放感に満たされる堪らない憩いの場所だ。
浜は珊瑚の真っ白な砂で左右にさんご礁の隆起の岩山が鬼岩のように砂浜を他の世界と隔絶させて壁を作っていた。さらに真っ青な蒼空に蒼とは本来こんな色だぞとでも言いたげに藍海が南風に押されて揺らいで光っている。きらきらとまぶしく輝く漣が寄せる波、返す波の起伏に揺れて輝く。その藍より深いと詠たわれるほどの琉球の海が小さな思いにやさしく応えてくれる。小さな入り江のその浜に珊瑚の化石を波で押し上げてチルーに限りなく無尽蔵に宝の山を与えてくれる。
 : 悠久の時の流れの中で母なる海が育んだ珊瑚の化石の宝物の輝きは幼いチルーにとってこの上ない極上の宝であった。だからチルーにとってはこの「我んぬ浜」は宝箱も同然で誰にも知られたくは無い大切な秘密の場所であった。 入り江は本当に狭くて小さいがチルーの望みを無限大に大きくかなえてくれる格好の恵みの場所であった。
|
その恵みの我んぬ浜に珊瑚の宝石を探して程なく小半時(一時間)が過ぎていた。
路地で村の童達とと遊んでいて夕飯時になって他の子達は皆んなアンマー(母親)やネーネー(姉)ニーニー(兄)が「夕げの時」を知らせる声を聞いてそれぞれの家に帰っていった。チルーだけが取り残されてひとり路傍にたたずんでいた。家に一人戻っても家には家の者達は誰もまだ戻ってはいないはずだから一時浜へ行って珊瑚の綺麗な宝石を探そうとやって来たのだった。
夕方は浜に下りてはいけないとアンマーに厳しく禁じられていたのだけれど少しだけ覗いてみようとやってきてすでに陽が傾き始めている。 チルーはそんな情景にも気がつかないほど一生懸命になって宝探しに夢中であった。
陽は翳り始めると早いあれよあれよという間に藍海の水平線の彼方へ落ちてゆく。まるで井戸の汲み桶が井戸の底に飲み込まれていくようにするべ落ちてゆく。
琉球の夕陽は紅い。満天が全て朱色に染まる。その朱色も金色に近いどちらかと言うと朱金といえるほどに輝いて見える。その朱金がコバルトブルーの藍海に映えて海一面が金紗の漣に照り輝く。
その情景はえもいわれぬ美しさである。さながら竜宮城の夕暮れのようである。 チルーはしゃがみこんで珊瑚の小粒を漁っていたがやおら金紗に輝く波打ち際の輝きに気がついて顔をその照り返しの波打ち際へ向けた。波が寄せるたびに潮が引き返すたびに泡立つ波際の砂が金色にきらきらと輝いて眩く光っている。  「わぁ〜美らさん」と驚きの声を上げて腰を上げて海に向かって立ち上がった。光り輝く波際の金色の光の帯をゆっっくりと顔を上げて見上げていった。顔をあげて視線を水平線のの方へ移して行くとチルーの眼前は真っ赤な夕景が燃え滾っていた。 「わぁ〜美らさん」と驚きの声を上げて腰を上げて海に向かって立ち上がった。光り輝く波際の金色の光の帯をゆっっくりと顔を上げて見上げていった。顔をあげて視線を水平線のの方へ移して行くとチルーの眼前は真っ赤な夕景が燃え滾っていた。
琉球の茜の空はまるで御伽噺のような夢のような雅らかさと荘厳さを併せ持って暮れてゆく。
字が小さくて読みにくい方は
[Ctrl]+[+]を同時に押すと拡大します。
茜染めし天に 生まり変わりたりば
何も欲しゃ無ん 我んぬ浜よ
チルーは満天の真っ赤な空を驚きの余りに次に生まれるときには夕焼け空のような茜色に染まって生まれたい。それが叶うならば他には何も望まないと我んぬ浜の神に願を掛けていた。
幼い童心が真摯に自然の厳かな情景に自分の偽りの無い本心を語りかけてゆく。それはまるでその後に続く自分の運命が想像もできないほど波乱に満ちて哀愁を帯び重く自分の人生の重荷となって圧し掛かり柔な体を押しつぶしていたぶり尽くして行くだろう事をおぼろげながらも微かに感じているようなそんな哀愁を感じさせる歌であった。
チルーは陽がするべ落としにすべって藍海の水平線の向うの涯へ隠れてゆく様を飽くことなく白い珊瑚の砂浜にたたずんで眺めていた。
陽は半分隠れてしまっている。その薄暮れの霞にに霞んで朧に燃ゆる大日輪が上弦だけをのこして紅にその姿をくっきりと見せ始めるとチルーは燃え盛る黒点に気づいた。気づいてすかさず祈りの歌を詠んだ!
てぃだ(太陽)よ てぃだよ
我んに習らしみ
字や言葉や 世ぬ人ぬ訓えよ
と言って請うた。
学びたいと言う切ない一途な思いが紅に燃え盛る朱の金剛日輪の中で燃えて揺らめく黒点の陰を捉えて、まるで太陽の中に字が描かれて呪文でも現れているかのようにチルーには見えた。その刹那に太陽に祈った。もっと学びたい。皆と同じように机に向かって筆で墨の真っ黒い大きく太い字を真っ白い紙に書いて連ね自分の心を綴りたい。と大きな目を開いて真剣に祈っていた。
そんなチルーの小さな切ない思いが哀れに思ったのかティダが応えるようにチルーの祈りの言葉が終わると同時に恵祥寺の鐘楼の鐘の音がするべ落ちる黄金の金剛日輪が水平線に消え行くのを送るように我んぬ浜に微かに聞こえた。  チルーははっと気づいて「ヤーケェーランシバ!アンマーグトゥ、アンジトウヤ」と言って豆の鞘ほどの大きさになって沈みかけるティダに背を翻して浜久比里の道へ駆けた。 チルーははっと気づいて「ヤーケェーランシバ!アンマーグトゥ、アンジトウヤ」と言って豆の鞘ほどの大きさになって沈みかけるティダに背を翻して浜久比里の道へ駆けた。
*註1
ヤーケェーランシバ!アンマーグトゥ、アンジトウヤ
= 早く家へ帰らなければ、お母さんが心配するわっ!
|
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
第弐話 アンマーイチデージ!ナトゥビングトゥー・・・
|
|
字が小さくて読みにくい方は[Ctrl]+[+]を同時に押すと拡大します。
|
息せき切って浜久比里を駆け上がり藪を掻き分けてサトウキビの畑へとでた。日が落ちた畑は暗かった。くびり道のトンネルを通って暗闇に慣れているはずの目にきび畑の畦は真っ暗に闇を連ねているばかりで幼いチルーに恐怖を覚えさせていた。一瞬たじろいで立ちすくんでしまったチルーは唇を噛み締めてきび畑の暗い畦道を走った。
頭上で風がきびの葉を煽って吹く。風にたなびくきびの葉の擦れ合う音がざわざわと不気味に響いて聞こえる。まるで逃げるチルーを背後から襲って追い縋ってくるような気配がした。チルーは泣き出しそうなくらいに怖かった。アンマーが夕暮れになったら浜に降りてはいけないと言っていたのを守らなかった勢でこんなに怖い目にあっている。自分が悪いんだと胸に後悔が締め付ける。
駆けて息が乱れる。怖さで息が詰まる。そして詫びる思いがさらに小さな胸を焦して窮地を脱しようと懸命にもがく。
夕闇と風が憐れな子羊を捉えようと追い回す。逃げても逃げても出口に辿り着けない。底なしの怖さであった。
チルーはたまらずに泪を零していた。チャーヒンギー(*註1)だ。左右の腕を打ち振って駆けてまだ足りない勢いを打ち振る腕に力任せに委ねていた。
溢れる泪が頬を伝って流れ出るのを拭き取ろうとして右手の腕を瞼に重ねて泪を拭い取ろうとした瞬間にうっかりと躓いてしまった。
体が宙に飛んでもんどりうって地面に落ちた。畦道で転んでしまった。 暗闇の転倒劇は昼間と違って地面との距離感が曖昧な分だけ衝撃が思いもよらずに大きい。手で体を支える間さえなかった。チルーは畦の赤土の上にしこたま顔をぶつけるように倒れた。その一瞬にチルーの少し上を向いているかわいい鼻先が地面と格闘してしまった。畦の柔らかいとは言えないまでも硬くはない赤土に顔面がめり込んでゆく気がした。脳裏を稲妻の閃光が突き抜けた。「あがっ!」と大きな叫び声を出して呻いた。 暗闇の転倒劇は昼間と違って地面との距離感が曖昧な分だけ衝撃が思いもよらずに大きい。手で体を支える間さえなかった。チルーは畦の赤土の上にしこたま顔をぶつけるように倒れた。その一瞬にチルーの少し上を向いているかわいい鼻先が地面と格闘してしまった。畦の柔らかいとは言えないまでも硬くはない赤土に顔面がめり込んでゆく気がした。脳裏を稲妻の閃光が突き抜けた。「あがっ!」と大きな叫び声を出して呻いた。
倒れて衝撃を受けたが幸いに傷はどこにも無かった。チルーは倒れた場所がこの畦道の土の上でよかったと胸を撫でた。
畦道ではなくて村道で転ぶと珊瑚礁の岩を砕いて敷き詰めているので大怪我になるところであった。またアンマーに要らぬ心配をかけるところであった。
チルーはしこたまぶつけて痺れて痛みが疼く鼻頭を小さくて細い指先でつまむようにして鼻頭に付いている赤土を拭いながら立ち上がった。
左の足の膝を持ち上げてその上に右手を重ねて体を立たせようとすると左の手の甲に紅い花が滲んだ。紅い花はふたつ、みっつと続いて左手の甲一面に広がっていった。
「血?」とすぐさま理解した。右手の平で鼻を拭うと手の平が血に染まった。その鮮血をまともに見てチルーは再び「あっが〜」と言って呻いた。血を見ないまでは痛みも少ない。しかし一端己の体内から迸り出る鮮血に気が付くと誰しもが気が動転して自分の身に起こった事が大袈裟な事の様に感じて驚く。
賢いチルーといえどそういう場合は同じであった。
血に驚いたチルーは風に煽られて逃げていたことなどすっかりと忘れて吹き飛んで痛さはそれほどでもなっかたのに突然火のついたように泣き出してしまった。真っ暗なサトウキビの畑の中にチルーの憐れな助けを求める声が響いた。
しかしきび畑は無情にもチルーの鳴き声を風のざわめきで掻き消してしまった。こんなに幼くって憐れな子羊の懇親の叫び声はか細く切なくきびの群生の間隙で消滅して消えていった。もはやタスクル者は皆無であった。そう思うと一段と寂しさが泣き声を大きくさせた。
こんなに大声をだしてはあのアンマーの優しくチルーを諌める声が聞こえてきそうでなんだか後ろめたくなっていた。だが泣き叫ぶほかに小さなチルーがこの窮地を脱する術はその時は考え付かなかった。啼くほかにないと悟ったチルーは自分の頭が大音響で壊れてしまいそうなほどに喚いていた。
*註1
チャーヒンギー
= 一生懸命に夢中で逃げる!
|
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
| |
第参話 チケーネン、ククルユルシンドォ
大丈夫、安心しなさい!
|
|
字が小さくて読みにくい方は[Ctrl]+[+]を同時に押すと拡大します。
|
權宗が畑の雑草抜きを終えて帰り支度をしていると何処からか小さな子の泣き声が聞こえる。權宗ははて何処から聞こえるのかと耳を欹てて聞いた。風に乗って流れてくるのか声が微かに聞こえたり止んだりしている。これは「デージナトゥビンワラバーヌクイヤシガ」と仰天した。こんな夕暮れに何処ぞに居るのかと辺りをうかがったが見渡せる処に人影のないことに気付いた。
「シタリ、ウージヌヌナカヤッサー」と見当をつけて捜し求めた。一目散に畦道を走る權宗はまるで鬼人のように早かった。他人の子といえども一大事・・・。權宗にとっては「ドゥマンギル」(驚く)「イチディージ!」(一大事件)出来事である。我子が大怪我でも負ったかの如くに懸命に駆けて捜した。
程なく浜に近くなってくると段々と泣き声がはっきりとしてきた。声の質からして女の子だなと識別できた。きび畑の畦は狭い權宗のように大人の大きな背丈では両側のきびの葉が重なり合っていて腰をかがめて走らなければならない。
& それにきびの葉はとうもろこしの葉に似ているがとうもろこしの葉のように柔らかくはない。硬くて当たり様によっては紙が手を切るように葉が刀の刃のようになる。
皮膚にこすると皮膚が破れて傷になるほど危険だ。そんな危険や苦労を今の權宗には省みている余裕はなかった。それほど子供の泣く声に自分の事の様に立ち向かっていた。声はすれども姿が見えぬ。權宗は立ち止まって大声を張り上げた。。
「ヌーヤガタイ」(誰ですか)「ウンジュ、カメーインドォ、クイアギティシミソーリョ」(あなたを捜していますから声をあげて応えてください。)と声を張り上げて叫んだ。だが風のざわめきが權宗の声を遮っているのだろう。はたまた自分の泣き声が大きすぎて權宗の呼びかけに気付かないで居るのだろう。どちらも正解であった。權宗は耳をさらに欹て声の方角を確認した。これは確かに畦の突き当りほどの場所から聞こえる真っ暗なきびの葉のトンネルを鳴き声を頼りに進んだ。
だんだんと近づいて声がはっきりと聞こえた。さらにきびの葉や枝を右に左に掻き分け掻き分け進むと暗いきび畑の畦道に紅い小さな可憐な花畑が權宗の目を射た。闇に浮かぶチルーの紅い花柄の着物地が權宗にとっては畑の畦に咲く可憐な草花のように鮮やかに写った。チルーの泣き竦む人影が權宗の優しい瞳にくっきりと見えた。
「アイエナ〜」といってチルーに近づいた。チルーはそんな權宗の姿にますます驚いてしまって一段と大声で泣き叫んだ。
權宗はとっさに「アキジャビヨーネーンナランシガ」(あれま〜もうだいじょうぶ)と言ってチルーの頭を撫でながら体を屈めてチルーの泣き面を覗いた。チルーは少し安心したのだろう。。 すぐに泣き止んだ。泣き止んで上目使いに權宗の目を覗く。權宗の微笑みながら近づく顔に安心して泪を小さな手の甲で拭った。その仕草を遮って權宗が腰の手ぬぐいでゆっくりとやさしくチルーの濡れた頬と流れ出る鼻汁とを一緒にふき取ってくれた。泪を拭いながら優しい声で權宗は「チケーネン、ククルユルシンドゥ」と言いながらチルーの背中を優しく擦ってくれた。続けて「ウンジュヌヤーヌアンネーシミソリョ(*註1)」と言うとチルーの手を両手に掬って包み込んで大きく口を開けて微笑んだ。 すぐに泣き止んだ。泣き止んで上目使いに權宗の目を覗く。權宗の微笑みながら近づく顔に安心して泪を小さな手の甲で拭った。その仕草を遮って權宗が腰の手ぬぐいでゆっくりとやさしくチルーの濡れた頬と流れ出る鼻汁とを一緒にふき取ってくれた。泪を拭いながら優しい声で權宗は「チケーネン、ククルユルシンドゥ」と言いながらチルーの背中を優しく擦ってくれた。続けて「ウンジュヌヤーヌアンネーシミソリョ(*註1)」と言うとチルーの手を両手に掬って包み込んで大きく口を開けて微笑んだ。
*註1
ウンジュヌヤーヌアンネーシミソリョ
= あなたのお家へ案内して下さい。span>
|
小さな手を優しく引いて權宗は体を右に左に捻りながらきびの葉をを掻き分けて真っ暗になったトンネルのような畦道を進んだ。 きびの畦は長い。特にこの時代の畑の区切りは今のように区画整理が行き届いてはいまからその長いトンネルはいま想像でき得るものではない。とりあず曲がりくねってたまっすぐな畦とと考えてほしい。沖縄でも僅か30年程前には場所によってはそういう昔の区割りをそのままに残すウージ畑を見ることができたが残念ながら現在では何処へ行っても。昔の面影のウージ畑を見る事はない。
程なく村道へ出た二人は一様にお互いを見合って笑顔を作って声を出して笑った。 特にチルーはやっと真っ暗なトンネルを脱してほっと胸を撫でていた。 權宗は「ウンジュヌヤー、マーカイガ、ウムチルー」(思鶴様あなたのお家はどちらの方向ですか?)と聞いた。チルーの名に「思」を付けたのは子供を呼ぶときの愛を込めた親近感最大にした呼び方であった。 權宗のチルーへの親近感と共に温かな思いやりが溢れるこの頃の時代は子供の扱い方のひとつを見ても素晴らしく人間愛を感じてしまう。この「思」と言う字に端的子供への共有思想が現れていて驚く。当時は貧困の時代沖縄民族学に詳しかった外間守善氏がその著書「南島抒情」に書いて居るような殺伐とした人間関係の時代背景であったならばこのように子供を大切にする冠称など用いる事などなかったであろうしそのような世の中では思という字体など必要ではなかったであろう。こういう僅かなうわべだけを考えてみてもそれは十分推し測ることが可能である。そういった文字のひとつひとつを事細かに見直して中世の琉球人達の真実の温もり溢れる人間愛を我々現代人は掘り起こして学ばなければいけない時代の岐路に立っている。
おっとついつい日頃の鬱憤を紙面で吐いてしまった。横道はさておきチルーは權宗の問いに「ヒジャインカイ、チーチー、ウクリーソリョウ」(左です。小父さん、送ってくださいませ。)と言った。權宗は「アイッ、ワカトービシガタシカミティミチョリシガ?。」と言って笑った。よその村の子ではないことを道を聞くことで確かめてみたのであった。 權宗は再び小さな手を引いて歩き出そうとして立ち止まって「ウムチルーグワー、ワンヌセガニクシガリヨゥタイ・・・。」と言ってチルーの前で地面に尻がつくほど身をかがめてチルーに背中へ縋れと優しく促した。 チルーは遊びつかれ泣きつかれてさらにお腹も減っていてこれはありがたやと感激してすぐさまに權宗の背中へ飛び乗った。その勢いが余りに強くて權宗は思いがけづに両手を地面についた。チルーの勢いに嬉しい重さを背中に感じた權宗は「アイッ、テゲーウムサッサヤウンジュヌ」(あれっ割と重たいねぇ〜)と言って右手を地面に支え左手を己の左ひざに支え「よいしょっ!」と声を威勢良く張り上げて体を起こした。
首に縋るチルーの手が權宗の咽喉を締め付けているが權宗はそんな事はお構いなしにチルーの体を両手を後ろに回した後ろ抱きに抱えて村の松田の屋敷・チルーの両親が待つ家へと急いだ。 歩き出すとチルーの首に縋る手が力なく解けチルーの可愛い頭が背中をすべって項垂れていった。權宗はチルーの疲れ方に可愛い幼子の無邪気さを感じてなお一層泣き叫んでいた憐れを回想して思わず子守唄を口ずさんだ。「ウンジュ、ウムチルー様よチバリヨーチバッテイキヨ。ヌチドォタカラヤシガ。」と呟く。まるで權宗は先に待つチルーの一家の絶望を見抜いているように呟いていた。勿論、言葉を吐いた權宗自身そんな悲しいストーリーが今自分の背中で夢見心地でよく寝ているチルーの身に及ぶだろうと言う事など考えてもいなかったのだが。
字が小さくて読みにくい方は[Ctrl]+[+]を同時に押すと拡大します。
「ハイヨーサイヨーワッタァヌセオイヌ、
ミヤラベーェー
イッペェーニンジンサイヨーサイッヨー
ナクンチャアンメーミラビヨーサイ
ニントーンヤーサイ、ミヤラビヨー
ムルシアワシナーイミミチュクリヨーサイ
イッページョートゥヤーサイヤーサイ
ヤイヨーサイヨー、
ハイヨーヤイヨーサイ

( [方言簡訳]
可愛い童 よ
たくさん眠って
たくさん良い夢を見てください。
それが一番あなたの幸せでしょから
ぐっすりと眠ってくださいね。)」
子守歌を気持ちよさそうに唄いながら村へ向かって急ぐ權宗は歌いながらもよくもまぁこんなにちいさな子供がこんなにも長い道のりをひとりであんな所までどうして行っていたのだろうと不思議だった。不思議に思いながら「アリエンヤシ、ウヤヨ!ヌーシビトゥガシ?」(有得ん。親は何をしているんだろう?)とチルーの両親に対して少し腹立たしかった。
松田と名乗ったから農夫ではない士族に違いはなかったが松田の姓は知っていたが村はずれで一人暮らしの農夫には士族との面識などあるはずはなかった。ほどなく屋敷が見えてきた。すでに闇は濃さを増してチルーの家の白い珊瑚礁の岩の石垣さえその陰を膨らませていた。
「ウムチルー様ウンジュヌヤーヌメェーヌ、エービンタイ」(貴女様のお家の前に着きましたよ。)とチルーの頭の方へ首を傾がせて優しく声をかけて起こそうとした。チルーは熟睡している。ちいさな寝息があの先ほどの恐怖を少しづつ解き放っているようであった。「はぁっ・・・」と吐息を強く吐いた權宗はぐっすりと気持ちよく寝ているチルーを起こすのが勿体無くって少し唇を綻ばせて「寝かせておこうか」と呟いた。門の前に立った權宗は外と内を仕切る門の中の庭に衝立状に在る「ヒンプン(*註1)」を背伸びして屋敷の中を窺って「松田様!權宗と申す者でございます。お宅様のお嬢様を訣け合ってお連れさせていただきました。」と夜気に遠慮がちな声でしかし力強く申し述べた。
第四話「上り浜ぬ西小ぬ(アガリハマヌイリグワァーヌ)權宗と申します。」につづく
|
|
字が小さくて読みにくい方は[Ctrl]+[+]を同時に押すと拡大します。
|
[*註1:「ヒンプン」:屋敷の正面の門と母屋を隔てるように衝立状に築いた壁。悪霊の進入を妨げる信仰上の壁。門から丸見えの家の中を隠す目隠しでもある。]
|
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
|
第四話 「上り浜ぬ西小ぬ(アガリハマヌイリグワァーヌ)權宗と申します。」
|
松田のお屋敷のアンマーの千代は門前を遮って天へ聳える大きなヒンプンがじゅまるの梢の間から何やら我が家を窺っている声があるのが見えて竈屋の板戸を開けた。 薄暗く闇が広がったチルーの家の前庭にかまどの薪の赤々と揺らぎながら燃える炎の紅の明かりがパチパイッと火がはぜる音とともに輝いて見えた。
チルーの母・千代は暗くなっても戻らないチルーの行方に気を揉んではいたものの夕げの支度に追われていて捜す事をチルーの兄の翔と翼に委ねて家で帰りを待っていた。 そんな心配の種があった時にその安否を告げに来たものが呼んでいるのであろうとこよなく期待して開けた板戸の淵の上の方へ両手を縋って身を持ち上げてヒンプンがじゅまるが聳える珊瑚岩の石積みの上越しに人影を見ようとして背伸びした。 
だがその場所からは表が見えない。業を煮やしてアンマーの千代は板戸を押し退けるようにして庭へ走り出て門前へと駆けた。ヒンプンの石垣の左側から表へ出ようとして千代は厳つい男が立っているのに気づいた。小走りを止めて腰を少し縊らせながら顔を斜めに傾いで男の顔に会釈しながら近づいた。近づいて男の背に童が背負われているのが見えて瞬間にその背に乗っているのが我が子のチルーであることを察しって「どなた様か存知ねども我んぬ思童(ウムワラベー)をお連れ戴いた情け、イッペーニヘーディビタン(ありごとうございます。)」と言って立ち止まって丁寧に腰を折り頭を下げて礼を述べた。
權宗はそんな千代の美らさぬ姿にかなり頬を紅くした。そして眼をこれ以上は大きく出来ないぞと言わんばかりに見開いて「アイエナー、レイヌグトゥマシヤエビーンサイ、グトォ、ウムチルーヌネムティグトゥ、ウケテミソウリョウ(イヤー、奥様ご丁寧なご挨拶恐縮です。御愛嬢様の思鶴様をお連れ申しましたのでお受け取り下されませ。)」と大きな笑顔ではにかみながら千代に告げた。
千代はそんな權宗の素朴な仕草にすっかりと安心して權宗を気に入って「中へお入りくださりませ。」と言った。 しかし權宗は千代の言葉に肯いて中へ入る事は出来なかった。  士族と農民の身分の違いも勿論の事それ以上に權宗を拒絶させたのは男女の関係であった。旦那の留守にその家の門前を破って中へ入ってはならじと幼き頃より父母に習っていた。常日頃そういう当たり前な事が人はなかなか守れないものだが、權宗は違った。身なりは農夫で土くれて埃っぽい雰囲気ではあるが気骨はそんじょそこいらの士族にさえも並ぶものがないほど頑なに頑強な志と深い仁愛を備えた人物であった。 士族と農民の身分の違いも勿論の事それ以上に權宗を拒絶させたのは男女の関係であった。旦那の留守にその家の門前を破って中へ入ってはならじと幼き頃より父母に習っていた。常日頃そういう当たり前な事が人はなかなか守れないものだが、權宗は違った。身なりは農夫で土くれて埃っぽい雰囲気ではあるが気骨はそんじょそこいらの士族にさえも並ぶものがないほど頑なに頑強な志と深い仁愛を備えた人物であった。
權宗は屋敷の縁側まではチルーを運んであげたいとは思ったが僅かな情けが人に仇することもあろうと考えて固唾を呑んで固持して背中のチルーを器用に前抱きに抱き替えて千代の胸へ抱かせた。
抱かせた刹那に千代の綺麗な瞳に魅せられ危うい自分に恥じて千代に深々と会釈をして去ろうとした。その時後ろから男の声が聞こえた。
「アイヤ〜チルーグワーモドラリシバームネナデリティヤシガ(あ〜チルーが戻っているよかったなぁ〜)」と大ききな声がした。 千代はそんなふたりの男の子の無作法な様子にすっかりと申しわけなさそうにして「これっ、翔と翼。あなた方もこのお方にお礼を述べてください。このお方がウムチルーをお連れして下されんですよ。」とチルーを捜しに言って見つけられないで捜しあぐねて帰ってきたふたりのチルーの兄に言った。そう言ってから千代は自分がまだこの恩人の名さえ尋ねていないことに気づいて自分の慌てぶりやら喜びようやらに尋常ではない子共に対する親の心の憐れな慌てぶりを露見していた自分にやっと気がついてこれはこのお方に大そうな無礼をいたしてお詫びのしょうもないと恥じた。
千代は改めて權宗へ深くお辞儀をして無礼を詫びて名を尋ねた。 權宗はそんな改まった千代の心のただしさにまたもや苦笑いを隠せず後ろ頭を掻きながら「名乗るほどの気高き名ではありませんが我が親が私に託した思いは恩納岳ほども高く聳えて、誰の名前よりも気位貴く天に聳えるように名づけられておりますなれど名乗る機会の乏しき事多くこの機を絶好の機会と思って名乗りますれば美しき奥方様の胸の内へ深く御刻み戴いてお聞きお留め下されたく存じます。」と長々と前口上を述べて勿体を少しつけながらまるで舞台に上がっているような感じの役者振りを見せて「東り浜ぬ西小ぬ(アガリハマヌイリグワァーヌ)權宗と申します。」と名乗った。
東り浜ぬ西小ぬ」は權宗の家の屋号だ。この時代の農民は姓はない 。その時代には農民たちは名よりもすべて屋号で呼ばれていてウッカリスルト自分の名前が何と言うものであったのかさえ忘れてしまうほど屋号の呼び名の方が馴染みよく響いて染み付いていた。  通り名としては少し変わっている權宗の屋号だった。あがりとは東の事で直訳すると東の浜の西の者である。東なのか西なのか?東西ハッキリして欲しいなぁ〜と思う屋号だった。傍でそんな權宗と千代のやり取りにおかしくて堪らずに翔と翼のふたりの兄は顔を見合わせて声を上げて腹を抱えていた。 その姿に無礼な振る舞を感じて驚いて千代はふたりの兄を諌めて權宗に中へ上がって貰ってお茶などを召し上がって戴きましょうと言った。 翔はこの時九歳で翼は一歳半離れて八歳の誕生日を明日に控えていた。ちなみにこの時チルーはまだ六歳になっておらず母・千代は三十歳にさえまだ二年もあった。若くて美しく優しい母である。そしてチルーの父・松田家の家長松田正順は母・千代より5歳上の三十三歳であった。 千代のたっての誘いにも固辞を貫く權宗は少し千代に申しわけがなさそうな気がしていたがそれはそれここで親の教えを曲げてはならんと頑なに拒んだ。そして改めて翔と翼にも深々と頭をさげ腰を曲げて会釈を繰り返してその場を立ち去ろうとして後ろへ後ずさり踵を返して千代達に背を向けた。周りはすでに闇に呑まれて通りの道筋さえ定かではなかったが權宗は遠目に村の目印を勘で見てすたすたと地を摺るように早足でチルーの屋敷を後にした。雨雲で覆われて月明かりが無かった。月が出る頃のこの時刻には空は満天がぶ厚い雨雲が初夏の生暖かい風に吹かれて闇の空を流れる雨雲がより黒く覆っていた。そんな漆黒の空をチラリと眺めた權宗は「あぁー今夜は一雨きそうだな」と一人呟いた。 通り名としては少し変わっている權宗の屋号だった。あがりとは東の事で直訳すると東の浜の西の者である。東なのか西なのか?東西ハッキリして欲しいなぁ〜と思う屋号だった。傍でそんな權宗と千代のやり取りにおかしくて堪らずに翔と翼のふたりの兄は顔を見合わせて声を上げて腹を抱えていた。 その姿に無礼な振る舞を感じて驚いて千代はふたりの兄を諌めて權宗に中へ上がって貰ってお茶などを召し上がって戴きましょうと言った。 翔はこの時九歳で翼は一歳半離れて八歳の誕生日を明日に控えていた。ちなみにこの時チルーはまだ六歳になっておらず母・千代は三十歳にさえまだ二年もあった。若くて美しく優しい母である。そしてチルーの父・松田家の家長松田正順は母・千代より5歳上の三十三歳であった。 千代のたっての誘いにも固辞を貫く權宗は少し千代に申しわけがなさそうな気がしていたがそれはそれここで親の教えを曲げてはならんと頑なに拒んだ。そして改めて翔と翼にも深々と頭をさげ腰を曲げて会釈を繰り返してその場を立ち去ろうとして後ろへ後ずさり踵を返して千代達に背を向けた。周りはすでに闇に呑まれて通りの道筋さえ定かではなかったが權宗は遠目に村の目印を勘で見てすたすたと地を摺るように早足でチルーの屋敷を後にした。雨雲で覆われて月明かりが無かった。月が出る頃のこの時刻には空は満天がぶ厚い雨雲が初夏の生暖かい風に吹かれて闇の空を流れる雨雲がより黒く覆っていた。そんな漆黒の空をチラリと眺めた權宗は「あぁー今夜は一雨きそうだな」と一人呟いた。 |
[*註1:「ヒンプン」:屋敷の正面の門と母屋を隔てるように衝立状に築いた壁。悪霊の進入を妨げる信仰上の壁。門から丸見えの家の中を隠す目隠しでもある。]
|
第五話「待たれよ、權宗殿。」につづく
|
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
|
第話 吉屋思鶴の生涯の真実は如何に!「第1部美童のチルー」第5話「待たれよっ!權宗殿」.txt
|
雨は農民の權宗にとっては恵みの雨である。雨が降るか振らぬかでは作物の成長に大きくかかわって出来不出来がそのままに雨の量で決まってしまう。 
生あったかで湿り気を帯びて重たい夜気をはらんだ村のフク木の並木道を月の無い漆黒の闇の中を權宗は何の迷いもなくすたすたと歩いて村はずれの恵祥寺の近くにある我が家へ急いだ。畑の畦道に農具をほっぽり投げたままにしていたが、まぁ明日ででよかろうと思って」取り行くことは無かった。 真っ暗なフク木の並木路をチルーの屋敷から我が家へ半分ほども進んだ頃に權宗は前から自分と対峙して歩を進める微かな足音を聞いた。珊瑚の岩礁を敷き詰めた道を確かな足取りの草鞋の路の泥土を摺る音が段々と自分のほうへ近づいてくる。 気配に察したのは權宗だけではなかった前からくる見えない影も対峙してその距離を縮めて歩み權宗の影を感じて路の端へ拠った。權宗はその影とぶつからない様に反対側へ体を寄せて歩いた。
男の影が近づいて横に並んで遠ざからんとしたその時に影が声を放った「これは權秀殿では御座らんか?」 
そう言って呼び止める声には權宗はさっぱり聞き覚えが無くって正体不明の主であった。「はて?暗闇に呼び止めなされるお方様はどちら様で御座いましょうか?」と尋ね返した。 男は一端離れて過ぎた距離を急ぎ取り戻して權宗の眼前へ姿を晒した。男は權宗に顔が見える距離まで近づいて確かに東り浜ぬ西小ーぬ權宗に間違いないと確認できると空かさずに深々と頭を下げて会釈した。
權宗は暗闇越しの物腰だけでも相手の男が士族の雰囲気を醸していることは感じていたから「はてっ、士族に我を知る者が在るとすれば納税奉行の下級の者しか思い当たらぬが他に誰ぞ知る者が在ったのかな?と首を傾げて相手の男を見つめた。 男は「これは失礼つかまつりました。私は北山の座喜味のグシク(城)に務める者で松田正順と申す者で御座います。」と名乗った。
「アイヤー、松田様と申されるはもしやウムツル様のお父上様で御座りまするか?」と言った。言うが早いか權宗はその場に平伏した。松田正順といえばその名も聴こえた北山の超エリート。若くして科子(琉球官吏への難関登用試験)を突破した希代の誉れではないのか?權宗は頭を地にすり着けながら考えていた。しかしながら松田正順は「權宗殿ここは無礼講に願いまする。」と言い置きしてから權宗の問いに首を傾げて眼を見開いて驚いた。 
何故に權宗殿が我が娘の鶴をご存知であろうか?と思い勢いお互いに質問の応酬となってしまった。
權宗は粗相に気づいて「ご無礼仕りました。」と詫びてから事のいきさつを言葉少なめに正順に説明した。それを聞いて甚く恐縮した正順は權宗の恩義を深々と感謝して礼を述べた。そして自分が何故權秀殿の名前を知っているのかと言う経緯をとうとうと語りだした。真っ暗なフク木の並木路に骨太な男の声が響く。
仔細はこうであった・權宗は根っから善人で人を援ける豊かな思いやりとやさしさに包まれながらも気骨は士族よりも志が高いほど頑なで城の役人にとっては何とも御しがたく誉れ高い村人として評判であった。ある飢饉の年に村中が飢えに苦しんで納税も滞りがちなくらいな時に村人の窮状を救わんとして一人立ちあっがてグシク(城)へ出向いて減税の請願に現れたことがあった。当然その時代は直訴はご法度とされていたから我が身の命を惜しまずに極刑を承知で嘆願する姿に当時の城詰めの役人達はこぞってその勇気に感服し琉球の賢人として有名な時の摂政羽地朝秀が權宗を琉球人の誉れと讃えその罪を咎めなかった。誰もが一様に權宗の行ないに琉球人たる者かくありたし・・・と感心して眺めていたことがあったのだがその時以来、正順もすっかりと權宗という名前と人物像が鮮明に胸に刻まれていて機会あるなら時を得て泡盛などを一緒に呑みたいものだなと常々思っていたことを權宗に告げた。
正順は權宗のファンの一人であったのだ。それで顔もはっきりと覚えていてその特異な髭の濃い琉球人的でありながらもどこが違った風貌は闇の中でさえ判然とするほど確かな存在感が認められた。暗がりでも誰と解るほどの存在感がある權宗も凄い人物だと言えるが、闇夜の道すがらすれ違いざまにそれを見て取る正順の気配を読む気迫も凄い。男たるもの常にこれ位の鋭い気配を滾らせていたいものである。
そのいわれを聞いて權宗は苦笑いして頭を掻いて笑った。その笑い声が闇の中を大きく通り抜けてふく木の梢に羽を休める琉球梟を驚かせて羽ばたかせた。真っ暗な天を真っ黒な大きな羽が影を創って写る。バサバサッと不気味な羽ばたきの音が權宗の天に突き抜ける笑い声の後を追った。静寂の宵闇は束の間に震撼を破って繕う。穏やかなうりずんの闇夜は更に黒く透けて夜を深くしていた。 
權宗は家に老いた母が自分の帰りをいまや遅しと首を長くして心配して待っていることを正順に告げてまた次の機会に必ず出向いて酌み交わしましょうと約束してその場から急ぎ足で老母の待つ我が家へと急いて動いた。 人の縁とはかように結びつきやすいものである。縦横の細い糸が織りなして華やかな柄の反物ともなれば無地で無垢な純白の装束にもなる。運命とは織って纏って見るまで誰にも解らない不可思議な物であるのだろうか。そうだとすればこのふたりのこの闇夜の出会いこそ不可思議な縁と思えなくも無い。果たしてふたりの縁はどんな柄に染まってゆくのか朧な影さえ見え隠れする様な夜であった。
|
[*註1:「」:。]
|
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
第六話「アイヤー、ナチカサヌー豊亀お姐さん!」につづく
|
|
吉屋思鶴の生涯の真実は如何に!「第1部美童のチルー」
第六話「アイヤー、ナチカサヌー豊亀お姐さん!」
|
「チルーヨ、ナマカラーアシブマーユクヤシガ、アトゥーティケーサイ(鶴っ、今からあそび場へ行くから追って来なさい。)」  と屋敷の庭に元気なチルーの兄翔の声が聞こえた。 チルーは昼さがりの温もりの中で縁側に近い廊下の板床にまったりして半分居眠り状態に入りかけていた。夢うつつに聞いた兄の声にチルーは我が意を得たと思い飛び跳ねておきた。退屈で眠りそうであったがなんだか眠ってしまうのが惜しいような陽だまりがやさしい今日の日差しをを感じていたのだった。 「マチキミソリョウータイ、ワンネネムリシナランシガ、アソバネバムルチムククリシヨータイ、マッチィンミソリョータイ(待って私も行くから眠たいけど遊ばないとつらいのだから、待ってください。)」と大慌てで飛び上がって後を追いかけた。 チルーの兄達の翔も翼も足が特別に早い。成長期の男の子は特にこの時期に俊敏な躍動感が形成されるようだ。兄弟が競って走るからその勢いは目にも止まらないほどに俊敏だ。あっという間に二人の影が生垣の向うへと消えた。チルーは庭に下りようと草鞋を捜したが目線には草鞋を見つけることが出来ずに敢えて首を右左に振って捜すこともせずに裸足のままに庭の琉球芝の芝葉の長い芝生の上に飛び降りた。 と屋敷の庭に元気なチルーの兄翔の声が聞こえた。 チルーは昼さがりの温もりの中で縁側に近い廊下の板床にまったりして半分居眠り状態に入りかけていた。夢うつつに聞いた兄の声にチルーは我が意を得たと思い飛び跳ねておきた。退屈で眠りそうであったがなんだか眠ってしまうのが惜しいような陽だまりがやさしい今日の日差しをを感じていたのだった。 「マチキミソリョウータイ、ワンネネムリシナランシガ、アソバネバムルチムククリシヨータイ、マッチィンミソリョータイ(待って私も行くから眠たいけど遊ばないとつらいのだから、待ってください。)」と大慌てで飛び上がって後を追いかけた。 チルーの兄達の翔も翼も足が特別に早い。成長期の男の子は特にこの時期に俊敏な躍動感が形成されるようだ。兄弟が競って走るからその勢いは目にも止まらないほどに俊敏だ。あっという間に二人の影が生垣の向うへと消えた。チルーは庭に下りようと草鞋を捜したが目線には草鞋を見つけることが出来ずに敢えて首を右左に振って捜すこともせずに裸足のままに庭の琉球芝の芝葉の長い芝生の上に飛び降りた。

大慌てで家を後にして村の遊び場へ駆けて行く兄妹達の姿に母千代は「キーチキティンアソバリーンソーリョウーウンジュタータイ(みんな気をつけてよ。)」と声を掛けた。裸足で走るチルーを見て注意せねばいけないと感じたがあの慌てぶりに免じてあげようと思った。帰ってから注意すれば事は足りそうだ。アンマーは無用な咎め立てをして子供心に水を差すようなことはしないのだ。たくさん遊んでたくさん大きく育ってほしいと願う気持ちの方が最優先している。いつの時代も母の愛は偉大だ。 と思っていた処へヒンプンガジュマルの石垣に人影が入ってくるのが見えた。一瞬にしてチルーの叔母さんの豊亀姐さんである事に気づいた。なんと十年来の恩人の来訪だ。 千代は驚いて声を上げて喜んだ。「豊亀お姐さんっ。いらっしゃいませ。まぁーこんなに遠路をお訪ね戴きイッペェーウサンサーサイ。(とてもありがたくて嬉しい。)」と言って慌てて庭へ裸足のまま下りて豊亀姐さんを出迎えた。抱きつかんばかりに近づいてその体に手を触れて満面の笑みで豊亀姐さんを見つめて喜んだ。その千代の眼は泪さえ溢れて今にも声を詰まらせて泣き出してしまわんばかりであった。感涙に咽いでしまいそうなほど懐かしさが胸を突上げていた。 豊亀姐さんという人は千代の母の妹でいわゆる叔母さんに当たる者である。千代が4歳から那覇の仲島の置屋で芸奴の修行をしていた時の先輩であり後にはお師匠様になった人であった。 豊亀は千代の母に代わって那覇仲島での母代わりをしてくれて母と同じように温かくそして厳しく千代を一人前の芸者に仕上げてくれた大恩人でも在った。 千代が首里のご番所勤めの正順と恋仲になって結婚してこの読谷の村に来て以来約十一年ぶりの再開であった。豊亀は流石に十年の歳月が滲み出て貫禄が付いて大きく見えた。 だがあの人懐っこキラキラしたつぶらな瞳の輝きは紛れもなくあの十年前の豊亀姐さんの輝きだった。千代は堪らず堪えきれずに袂を右手跳ねて唇を押さえて潤んだ瞳で豊亀姐さんの眼をじっと見つめた。

笑顔の中にも泪するほどの別れの寂しさが再会を喜び合う二人の胸を突いてどちらも 女々しくサメザメトナ泣いて抱き合って再会を喜び合った。 千代が那覇の仲島の置屋へ修行に出されたのは四歳の夏。琉球の蝉たちが天をついて泣き喚くうるさい夏の暑い盛りであった。母に手を引かれて父と三人で叔母豊亀の置屋の吉屋という楼へ芸者の卵をして連れて行かれた。その道中の道すがら並木の琉球松に縋ってうるさく泣くセミの声が今でも千代の心に焼き付いて残っている。セミが鳴く声を聞くたびに仲島へ向かったあの頃の情景が懐かしく切なく思い駆け抜けてくる。つらく悲しい思い出ではない。新しい旅路への不安は少しは感じていたがそんなことの仔細な憂いよりも兎に角に新天地での夢のような世界へ至る憧れのほうが万倍も大きくて期待に胸を膨らませて父母と歩いたあの夏の琉球松の並木道が美しい風景と共にさやけく思い出として千代の胸に去来するのである。 あの頃は幼くって要領の解らない事が多かったけれど置屋の女将も姐御の豊亀も掛けねなく底抜けにやさしいかった。だから千代は両親とはなれて暮らしたことがそんなに哀しい思い出にはなっていなかった。哀しさよりも楽しさや驚きや温かさが多くて哀しみを感じる暇さえなかった。父母に逢えない寂しさを思う暇などはなかった。まるで竜宮城へ行った浦島太郎のように・・・。

今日の豊亀の来訪の目的を千代は解っていた。豊亀は思鶴を仲島へ連れて行く為にこうして読谷の片田舎の村までわざわざやって来たのであろう。これは千代に有無を問うことではなくてそのままにどんな親であっても反対する理由がない喜ばしい招きの使いの申し出であった。仲島へ入ると言うことは芸者として才能を買われて期待され声を掛けられると言うことだ。認められて鍛えれば必ず大輪の華となって輝きに満ちた人生が開けることを約束するものであったからその申し出に礼を尽くして来訪する楼閣の遣いの使者を拒むものは居ない。この時代の芸奴と言えば近世の著述の悪影響もあってまるで現代の性風俗と同列視されるがはなはだ笑止千万。全く違う。曳いて言えば辺プロやジャニーズ事務所が契約しに罷り越した様なものでいわゆるその時代のアイドル養成所への勧誘のようなものであったのだから大概の親であれば一様に我子の華やいだ世界への旅立ちを喜んだものだ。。表舞台への栄光への道筋が筋書き通りに用意されている。 チルーの母の千代自身が4歳からその道を踏襲して華やかな花柳界の花形を担っていた若き日もあった。ただ千代の場合は期せずして恋に落ちて栄光の座を取り替えて女として愛に生きることを選択して妻となり3人の母となった。また違った幸福に満たされた人生を歩んでいたから我娘ノチルーがその道へ入ることに対しては何の違和感もなくただ喜ぶばかりのことでさえあった。

だが豊亀の申し出に千代は即答を避けた。ウムチルーを仲島へ行かせる事にはなんら反対することはなかった。 預かってくれるのが豊亀お姐さんであることは千代にとっては願っても無い申し分の無い条件提示であった。それは契約金を提示されるまでもなく。というよりもむしろ頭を下げて豊亀お姐さんにお願いしたいとさえ思うくらいの気持ちはあった。 だが千代はその時何故だろうか首を縦に振らなかった。だがはっきりと断ったのでもなかった。今この事を決めてしまう事に執拗に言いようの無い拘りが脳裏を駆け巡っていた。それは確かな理由ではなくって千代の勝手な妄想だけであったかも知れなかったが。何だか今返事をして決めてしまうともう二度と一生の間にはあの可愛いウムチルーには逢えないような気がしていた。そしてその微かな不安はこの問題を親の私が今即答しなくともチルー自身がいずれ自分自身で決断を迫られて決意を固めて豊亀の待つ那覇の仲島・吉屋の楼閣へ行くことになりそうな胸騒ぎのような予感があった。微塵な霞の心の淵に佇んでいるチルーがこの問題を自分で考えて自分で決断して運命を自分の意思で刻んでゆく。そう思えてチルーの母千代はその場ははっきりと大恩人であり人生の師である豊亀の申し出に首を横に振るしかなかった。頑なに固辞した。千代の予感は陽炎のような実体のない結果を予想しているだけなのかも知れないが千代は幸福な毎日が夢のように過ぎてゆくことに自分の人生は満足しきってしまったような一抹の不安があったのであろう。豊亀の眼にはその千代の姿がぼんやりと繧蚊の群れが夕暮の木陰に群がって微かな闇を織り成しているように感じられた。その刹那を豊亀は押し切ることが出来なかった。豊亀には千代の考えている事が形としてではなく一陣のつむじ風が巻き上げる砂埃のなかの塵芥のような感じで伝わっていた。それは紛れも無く豊亀が口を挟んで遮ぎ切れるものではないことを豊亀は胸に針を通された様な痛みとして感じた。 親心とは不可思議で神秘を醸す。己の運命さえ釈然と図りがたく解り様がないのに愛する我子の運命はおぼろながら予感する。そしてその予感は的中した。

 |
[*註1:「」:。]
|
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
吉屋思鶴の生涯の真実は如何に!「第1部美童のチルー」
第七話「ハツミエヤシガ、チルーエ−ビンドォ、豊亀ウフウフンマータイ!」
|
[*註1:「」:。]
|
|
第七話「ハツミエヤシガ、チルーエ−ビンドォ、豊亀ウフウフンマーサタイ!」
|
豊亀との懐かしい思い出話やその後の楽しい読谷での暮らしぶりを止め処も無く語っていて千代は昔の同僚たちの行方などにも詳しく豊亀に教えを請うて尋ねた。 豊亀が話すには千代の去った後は仲島全体が火が消えたように冷えてなかなか回復できなかったのだよとあまりにも突然に引退した千代の事を本当に勿体無いことであった。と嘆いて見せた。千代を欠いた仲島では確かに華が忽然と消えた花器のようで底に残った剣山に代わりの華を生けるのに少なからず時が必要であったようである。いつの世でも大型の大器は稀にてすぐには宛がい難い者らしきようやも知れぬ。 そこはかとなく昔話を楽しそうに続けて居るところへ翔が鶴の手を引いてヒンプンの陰から飛び出して屋敷の上がり框まで走り来た。息を切らせもせずに「アンマー様、ハーキティンヌーカマンヤータイ(お母上様、お腹が空いたので何か食べたいのですが?)」と言った。

千代は「ワカイェービンタイ、マチキミソリーョ、マジン、クヌカタニ、エージシミソーリョウンジュターヌ、ウフウフンマーヤグトゥ(解りました、その前にこのお方様はあなた方の大叔母様ですからご挨拶をしてください。)」と言って豊亀の眼を見て嬉しそうに笑った。千代は「ユクゥーヌクトゥタザナンタイ(翼はどうされたのか?)」と心配して聞いた。翔は「アランシガ、ナマ、オニナットォーン(今、翼は鬼やっています。)」と大きな声で応えた。 かくれんぼの途中に家まで逃げ隠れておやつを求めているのである。千代は「アイエナーヨクゥーヨ、アワレナトォーシガ(あれま、翼はかわいそうに。)」と言いながら台所へ向かった。 千代が豊亀にお替りのお茶をもって現れる間の束の間に豊亀は翔とチルーに話し掛けていた。翔も鶴も豊亀の雅な装いに驚きの目を見張って見つめていた。 黒の薄絣の紋付の羽織が紅型染めの華やいだ絹に金紗がキラキラ輝いている着物をひと際に引き立て紅色と金紗が我んヌ浜で見たあの夕陽の照り返す白い珊瑚の砂浜の波打ち際のキラキラした輝きに似て取り分けてチルーの心を惹きつけた。

勿論若さは千代の十年前とは比べようもなくなっているがかっては豊亀も仲島では押しも押されもしない超一流の芸奴であったからただそこに座して居るだけでもその存在感は絶大に見えた。特に美しいものにこよなく心を砕いて奪われるチルーにとっては憧れの華がそこに忽然と咲き誇っている様にも写っていたほどであった。年齢さえ五十に手が届きそうな齢であったが雰囲気はまだまだ現役の花形奴にも引けを取らないほど輝いていた。 母千代が村の祝い行事の度に着飾って美しく変身して見せてくれていたがその華やかさとはまた一味違う貫禄のある落ち着いた風格を醸しだしている大叔母・豊亀のしなやかな貴品に満ちた美しさに一段と神々しいほどの都の優雅な美を見つけた思いがした。 チルーはそそくさと座敷へ上がって畳に両手をついて「ウフウフナー様チルーヤエービングトィハジミティンオミドゥーリイッペーウササヌヤータイ(大叔母様、鶴と申します。お会いできてとても嬉しいです。)」と挨拶した。

その立派な挨拶の言葉を聴いて豊亀大叔母様は感極まって眼が潤んだ。小鼻を右手の人差し指の背中で触れるようにして小さく深く首を縦に振った。「翔ヨー、ウムチルーヨー、初めまして豊亀叔母さんです。」と言って声を詰まらせ咽び泣いていた。女は嬉しいとすぐ涙が感情をあらわにして心を洗うのだ。女の泪は迸る母性愛の川の飛沫ようなものだ。岩を濡らした飛沫は渇くまもなくまたまた打ち寄せて岩を濡らして洗う。来る日も来る日も休むことなく岩の角が無くなるほど涙と言う潤いで包んで岩肌を磨いてくれる。この潤いの飛沫がいつしか岩をも研ぐ川の流れの飛沫ように人が角を丸くしてやさしく生きる為に必要な要素になっているのだと思われる。かくして母は涙もろくある所以である。FantasticFantastic |
[*註1:「」:。]
|
吉屋思鶴の生涯の真実は如何に!「第1部美童のチルー」
第八話「豊亀!郷愁に零す!」.txt
|
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
吉屋思鶴の生涯の真実は如何に!「第1部美童のチルー」
第八話「豊亀!郷愁に零す!」
|
豊亀は次の日の昼前頃に松田の屋敷を出た。 豊亀は那覇から同行した芸奴の女中と帰りの道中に千代の庭に咲いていた真っ赤な大きな花のそのあまりにも綺麗だった事が眼に焼きついてしまっていてその花の話をしながらその赤い大きな綺麗な花と千代の身を重ねて見ては、千代は仲島で花の命を散らせてしまったように見えたけれど見事に仲島とは異なる自然の美しい景色の読谷の村で再び蘇ったように咲いていると感じた。その花が咲く場所はやはり千代の庭に咲いていたあの紅い花の様に千代と言う名の母なる紅い花が咲く場所は、あのさやけくすがすがしい村の朝焼けの中が好く似合っているように思うのであった。 ウムチルーもあの千代のもとであの松田の屋敷があるあの村で真っ赤に咲き誇ったほうがより美しく咲くのかも知れないと思えた。長い道のりの苦労の多い難渋の来た道ではあったが久方に実りの多い晴れがましい心地がする帰り道の旅であった。 四歳の時に千代を仲島という特異な環境の中で母代わり姉代わりになって育て上げてその千代は十九の花の盛りに恋を知って仲島を離れてしまったけれど、あの幸せな姿をみれば十分だった。今は本当にこれが千代の人生にとって望ましい事であると思えて心から喜ばずにいられなかった。千代と正順の祝言の折にはそれまでの苦難がやっと花開こうとした瞬間にその栄光を捨てて飛び立っていったように思えなくもなったが昨日、あの日以来十年ぶり千代と逢い千代のの子供たちを見て豊亀はあの時の不安がただの想い過ごしであったと気づかされたようであった。 
ウムチルーのことは千代が言っていたようにチルーが自分で望んで仲島に来たいと言うまでもう二度と迎えに来る様なことは止めようと心に硬く誓った。あのチルーの可愛らしさを見た後では磨けば光る玉をみすみす見逃してしまう気がしないでもなくはないが殊更に残念な思いがこみ上げてきはするがそれはそれ、それもいたし方が無い事だと思い二度と後ろを振り返る事はしなかった。帰りの旅は流石に遠く長く感じた。でもその長い道中が豊亀にとってはあの千代の思い出を深く反芻させてくれて思い出の懐かしさに耽るのに丁度都合のよい長さに感じた。 収穫のないはずの豊亀の懐には心地のよい重さの温もりが旅の土産として入っていた。何とも人の心とは都合よく暖かなものである。この温もりのお陰で人は明るく生きられるのであろうか。 
比謝橋を渡って嘉手納の一本松の丘で同行の芸奴とふたりして読谷の緑の山蔭を眺めながら千代が握ってくれたおにぎりを食べてお昼の一休みをした。北谷の風光明媚な松並木を抜けて延延と続く田園風景を渡り宇地泊から牧港、浦添の小湾を通って天久の崖下から安謝の綺麗な珊瑚の浜沿いの道を行く頃には夕陽が慶良間の万重の島影を蒼く浮かび上がらせていた。 えもいわれぬさやけく茜の空が金紗に輝いていつまでも永遠に途切れないで続いてゆくように見える。 豊亀は同行の芸奴にここで夕陽を眺めて帰りましょうと言って珊瑚の真っ白な安謝の広い浜へ駆け下りていった。 大きな日輪をコバルトブルーの海原に照り映えながら沈み行く姿を観て豊亀は千代の幸せな姿にまた泪を零して喜んでいた。 人生を何処まで行っても千代のことは心から離れはしない。 
子を忘れる母など居やしない。
再会を束の間に喜び合って来たけれど心の奥底では再び千代と会う事がないような微かなさびしさが豊亀の胸を一本の細い筋となって切り裂いて過ぎてゆくような気がしていた。 夏の雲が水平線の彼方から天を頂まで突き詰めて積み重なっている。夕陽を背に浴び真っ白に輝くあの積乱雲が青黒く闇を織り始めている。 南風がそよいで漣を作り夕陽がその漣に映えて金色のきらめきを海一面に綾なしている。この心地よい風の声を読谷の千代や千代の子供たちも聴いているのだろうか。この海の鳴り響く鳴響きをみんなも聴いているのだろうか。豊亀は足袋を脱いで白く美しい素足を白い波立つ潮路につけた。 やわらかな塩水の足首を撫でる感触が無性に豊亀にとって昔の幼い日の思い出をむせ返らせて赤い夕陽のその中にたわむれる自分の幼き頃の姿を浮び上がらせて偲んだ。 
遠い日の懐かしい夕陽も懐かしい海も懐かしい空も懐かしい南風もみんな同じなのにいつしか人は心を変えてゆくのだ。と自分の境涯や仲島の女たちの境涯が無性に憐れな束の間の儚い夢であったように思えていた。 豊亀は波に戯れる同行の芸奴を眺めながら安謝の珊瑚の化石の真白い砂浜に膝を山折にして手を添えて腰を下ろして沈む夕陽を眺めて微笑んだ。キラキラと漣のような瞳の輝きが一縷頬を伝って零れた。 紅蓮の赤い夕陽がオレンジ色になって変わって行く。その姿を水平線の向うへと滑り落としてゆく。その落日の様はするべ落としのように早い。束の間の一大劇は眼を瞬く暇が無いほどに荘厳な美を見せつけながら幕を引く。夕闇が南風に乗って暮れてゆく。豊亀は辺りが夕闇に染まってきてもその場所から動こうとはしなかった。いや、動く事が出来ないほど懐かしい郷愁にしたって泣いていた。 泣いて泣き尽して泪なんてとっくの昔に尽きてしまって渇いていると思っていたのにとめどなく流れ落ちる涙が豊亀にはなんだかとても新鮮な涙の様な感じがした。女は幾つになっても母性愛の泪を枯らすことはないのだ。豊亀は自分が母として千代のことを千代の家庭の幸せを祈っているのだとつくづく知る思いがした。人の心がたとえ千変万化しようと母の母性愛は永遠に不滅で普遍なのであろうか。豊亀は暮れなずむ夕暮を背にしてまた背筋を伸ばして女将の顔に戻って仲島の自分を待っている吉屋の楼閣へ帰っていった。ほとんど沈んでいる夕陽の輝きが豊亀の銀かんざしのの飾りに映えてキラッと赤い煌めきを夕闇に瞬かせて光った。その銀かんざしの揺れる飾りの煌めきのように豊亀は吉屋へ戻って最後の女将としての一仕事を飾り女としても人としても最後の輝きを瞬かせるのであろうか。琉球の時代のうねりは仲島の楼閣吉屋の女将豊亀に新たな生き様を築けと望んでいるように大きくうねり始めていた。時は万葉の詩を奏でて琉球に新しい文学の息吹きをみせ始めようとしている。あとはただ誰がその時代の花形としてデビューして名を刻んでゆくのかだけであるやも知れん。時の民でさえその者の名は未だ知らず。まだ微かな訪れの期待の予兆さえなかった。だが確実に大きなうねりが動き始めていた。
|
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
吉屋思鶴の生涯の真実は如何に!「第1部美童のチルー」
第九話「優しいアンマー鬼の如しに観ゆる!!」
この稿は第1部 第九話書き下ろしです。
|
那覇の仲島の楼閣吉屋の豊亀大叔母様が久々に来訪して松田の屋敷でチルーの母千代と夜を徹して昔話に花咲かせて帰っていってから一週間も経った朝、久しげな雨の訪れで朝は空けた。雨の音は激しかった。激しく地面を穿って大きな音を響かせていた。 その音の激しさの中で天上からさわさわとざわめくような心地のよい雨音が訪れる。雨が茅葺の屋根を潜る音がチルーの耳に留いて幼い繊細な胸の中に子守唄のように響いてくる。板戸を押し開けて入ってくる地面を穿つ激しい雨音。天上から奏でる夢幻の子守唄。ちるーはどちらも聞こえていた。雨は琉球の芭蕉の緑の大きな葉やガジュマルの大樹の群緑の梢を敲く。葉を伝った大粒の雫が地面へ向かって急な流れを生じて滝のように地面に落下する。そして地面に溜まった雨水を弾いて飛び散って大地を流れて地へ潜り海へ辿り天へ昇る。悠久に繰り返される自然の摂理である。 チルーはこの自然の雨の音が大好きであった。何かしら琉球の雨は恵みを齎す。だが眠りが遮られる雨音は少し鬱とおしい気はする。朝から激しい雨音に目覚めを促されるようにチルーは眠りから覚めた。
雨の激しい音を聴いてチルーは今日は外へ遊びには行けそうもないなと寝惚け眼を擦りながら思った。沖縄の雨は激しく降った後すぐに上がってしまうことが多いのだがこの時期はそろそろ雨季が近づいていてチルーの幼い心にもその雨がすぐには上がりそうも無い事を感じ取る事が出来た。 板戸を開けると雨音がより大きく部屋の中を駆け巡る。雨ののザアーザアーと響く音に間切れて包丁がまな板を打つ勘高いトントンと鳴る音もチルーの耳に入って来た。聴いた音のする方へスキップして駆けた。 その包丁捌きのトントンと打つ響きに合わせてチルーは飛び跳ねて台所の千代の所へ駆け寄った。寝惚け眼でスキップしたチルーはまだ体が完全に起きていない勢で体がよろけた。よろけてまだ眠っている二人の兄の体の上へ転がった。。その衝撃でふたりの兄は眠りから覚めた。驚いて眼をこすって目覚めた。チルーが起き出した二人の兄に「ウミリーヨーサイ(オハヨー)」と布団の上に正座して朝の挨拶をした。兄翔の半開きの睡魔と懸命に戦っている寝惚けた眼をした顔を覗きこんだ。寝起きは誰しも不機嫌だ。特に兄翔は寝起きが悪い。覗き込むチルーの笑顔と元気な声に口元と眦が円を描く。翔は「ふみゅ、・・・」と奇妙な奇声をを発して布団を被ってまた寝転んでしまった。 そんな翔の姿を見て翔の頭から被っている掛け布団をチルーは思い切りよくはいでから兄の翼に「翼ニーニー、ウミリーヨーサイ」と言ってまたまた翼兄の顔に自分の顔がくっつくくらいに近づけて眼を大きく見開いて翼のの俯いた顔を覗き込んだ。翼兄は「ウミリヨー」と小さく面倒そうに呟いた。呟いてその言葉が終わらぬうちに素早くチルーに飛びついて抱きついた。「わぁ〜」とチルーは大喜びした。その声に翔が飛び跳ねて起きてその戯れに加わった。チルーに抱きついてじゃれている翼の脚を掴んで引っ張った。掴まれて引っ張られた翼の体は翔の上に重なった。翼は勢いそのままに今度は翔へ抱きついった。寝起きにまだ不機嫌さを払っていない翔は翼のじゃれ方少しウザイと思った。ちょっぴり怒りをみせた。「アッサ。タンガシケナサヌーナヨー(やめろっ。)」と少しむっとして感情をむき出した。
そんな翔とは逆に翼は朝から気嫌よすぎる?さわやかな雄たけびを挙げて翔の体に飛びついていった。完全に翔は切れた「アイヤッ、モウ、ユルサリンヤッサ(もう絶対に許せん。)」と言って翼に組みかかった。 その翔の怒り方に余計に面白さを感じた。と言うよりもおかしさがこみ上げて大声を出して笑って翔の絡め手を逃れた。迂闊にも弟を解放してしまった。翼を逃がした兄は跳ね起きて翼を追う。翼は表が雨なので家の中を逃げ回った。そのふたりの追いかけっこを手を囃して楽しそうにチルーが後を追いかけた。広くはない屋敷の中で朝の早くから騒動だ。大運動会が始まった。 常日頃からからアンマーは「家の中でトゥバトゥバスンナヨー(暴れまわるな)」と言って子供たちを戒めている。にも拘らずこんなに朝早くから走り回る我子達の暴れん坊の様子に雨の憂鬱も手伝ったのか母千代は珍しく苛立って三人を正座させて叱りつけた。 小言は早朝の起き抜けの松田の屋敷を押し包んだ。延延と小半時(訳三十分)も続いた。 一番座(奥座敷)から父正順がもう遮ろうとして姿を見せた。千代はこれは善い所へと正順に応えて父の責を子を戒めてください。とその場を委ねて台所のした働きの女中に朝食の膳を繕う用意を促した。 正順は千代の横に正座して膝を詰めて琉歌を詠みだした。
ハルヤハナザカリ ミヤマウグイスィヌ
ニエィシヌディフキル クイヌシュラシャ
和綴り
春や花盛り美山うぐいすの
匂い篠でほける
声のしおらしや
と聞かせた。
これに昨夜の御前様がまだ泡盛の香りかと千代はますます苛立ち怒りが鎌首を持ち上げて見えて「ナマ、ウリズンンヌ、サカリヤシガ、ウンナバアラネ(今は若夏の真っ最中、時期はずれの歌です。)」と言って正順を嗜めた。 正順ははっと我に返って「いかん昨夜の酔いが残っている」と気づいた。正順は千代の眼を横から盗み見てこれは昨夜の御前様の所業に立腹か・・・と気づいてなんと薮蛇なことであった。迂闊に不覚!と悟った。小さく咳払いをして慌てて
ハナンニエィシュラシャ ツィチンティティリジュラサ
ウスカジトゥツィリティ アスィディムドゥラ
和綴り
花も匂いしほらしや
月も照り清らさ
押風と連れて遊で戻ら
と詠んだ。 その歌に千代はますます口を尖らせ頬を膨らませて「それは昨夜の貴方様の為りではござりませぬか。」と衝き放つように言った。 拙い。助っ人のつもりで出た筈であったが薮蛇。逆に討たれている。そればかりではなく倍以上に仇になって返ってきた。「まずいっ。」と正順は肝が揺らいだ。一瞬たじろぎながらもにこやかさを子供たちに装い無理して眉尻を下げ口元を吊り上げて笑顔を作って咽喉の奥に魚の骨がつっかえた様な笑い声ともつかぬ苦し紛れの悲鳴を唸った。 はぁ〜と大きく息を吐いて「それでは」と気を取り直すように正順は次の句を披露した。
ニワヌマシウチニ ツィユヌタマウキティ
シュラシニエィタチュル ハナヌチュラサ
和綴り
庭のませ内に 露の玉受けて
しほらし匂いたちゆる 花の美らさ
と詠んだ。
それを聴いて千代はやっと膝を挙げてそそくさと女中と一緒に朝餉の準備にかかった。 その母の姿を眼で追った三人は難が去ったことに気づいて父の活躍を讃えて大喝采の拍手を送った。正順は子供たちが我が歌の素晴らしさに感じて拍手喝采していると勘違いして大いに満足げに笑顔満面にして何度も大きく肯いて子供たちの顔を順に繁々と眺めて喜びを顕わにしていた。 まもなくお食事の御膳が揃ったと女中が告げってくれた。
一様に膳に着いて「クワチッーサビラ(いただきます。)」と声を揃えて神に感謝を捧げて箸を手にして楽しい朝のひと時が始まった。朝餉の時は滴り落ちる雨もさわやかな響きに変える。少しではあったが雨脚が細くなってきつつ有りそうな薄明かりが窓のひさしから枝垂れ落ちる雫に映えて朝食で賑う松田の屋敷の大御膳の紫檀の艶やけき光を一層輝かせて見せていた。和みの一家の朝餉の和らぐ風景がそこには確かにあった。 |
[*註1:「」:。]
|
| |
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
|
吉屋思鶴の生涯の真実は如何に!「第1部美童のチルー」
第十話 水琴屈の章
|
まるで天が破れたように雨が滴り落ちて止んだ。 雨上がりの琉球の空はすこぶるに碧い。 雲はすこぶるに白く輝いて高く高く積み重なってわだつみをそのままに美しく見せる。そんな雨上がりの澄み渡る大空を見つめていてチルーは不思議な音色が何処からか響いてくるのを聴いた。まるで琴の弦を一杯に張り詰めたような尾を曳く、琴の弦を高く爪弾いたような音を聴いた。不思議な音にチルーは驚きながら音源を探った。何かが近づいてくるような錯覚に堕ちいった。音が同じ響きの音が間隔を広げて遠くから押し寄せてくる不思議な感覚の琴の音が聴こえた。耳を澄まして辺りを見回すが何者もいない。しかし、確かに音は綺麗な琴の音を奏でている。
「ピッキーン」と一音が長く尾を曳いてチルーの頭の中へ飛び込んでくる。まるでチルーがいつも心に描いている幻想の世界の扉の隙間から漏れてくるような夢のような調べに聴こえる。 でもそのまえに綺麗な高い音のその前に水を打つ音も確かに聴こえていた。「ピッチャンー」と雫が水面を敲いて破って弾かれ波紋を広げてゆく時の音のようである。確かに何度聴いても最初に水の雫が水面を衝いて落ちる音が聴こえる。そのあとに「ピッキーン」だ。どこだろう?チルーは無心で耳を澄ました。顔を項垂れて耳を澄ますと音の流れ来る色が鮮やかに見えるようであった。あっ、と声を上げて驚いた。チルーの音源を探るために首を傾げて耳を澄ましている視線が庭の置石から母屋のひさしの西側に置かれている大きな水瓶にゆっくりと達してベンガラ色に届いた。上がりかまちの先を辿ると大きなベンガラ色の水瓶が置いてある。チルーの視線はそのベンガラ色の水瓶に釘付けになった。チルーは大発明が完成した時のエジソンの驚嘆の顔か、それとも悪霊島を望遠鏡で覗いていているキャプテン・スパローのような驚愕の眼を見開いてベンガラ色の大きな水瓶を見やった。確かに雅な音色が水瓶から跳ね上がって聞こえてくる。やったあー見つけた。と喜んでチルーは瓶の傍へ駆け寄った。雨の残り雫の水滴が藁葺き屋根の軒下を離れて直下にある水瓶にゆっくりと勢いよく伝い落ちていった。その刹那落下した雫が弾けて水瓶の中で音を奏でていた。水瓶の水の量が少なくてその分瓶に溜まった水面に跳ねた水滴の音が水瓶の円胴の内部に反響してまるで水琴窟のような美しい音色となって雨上がりのチルーの屋敷の庭に鳴り響いていた。暫し呆然と見入っていた。雨の雫は時間とともに量を減らしてゆく。それとともに段々と間隔は途切れ水琴窟の雅の琴の音色は間隔を開いて少しづつ途絶えがちになって終わる。雨の雫がついには無くなる。そんな光景にじれったく思ったチルーは終幕した雨上がり幻想の雅の調べに心残りでとても残念に思えて晴れ上がった青い空を恨めしく睨んだ。
雲よ湧きあがれ 風よ吹きすさべ 雨を降らし給もれ 琴の音を我んに聴かせ給え
と天に向かって祈って叫んだ。 だが一度上がった雨はすぐには降る兆しはなかった。それどころかますます青空が広がり太陽がその光を滾りはじめてまたたくまにあたりを干上がらせてゆく。 チルーは水瓶に小さな手を差し入れて中の水を小さな手のひらに掬って自分の頭上より高く挙げて手のひらの水をベンガラ色の大きな水瓶に落としてみた。ジョボッジョボッと水が滴り落ちた。音はベンガラの水瓶の中で少しは反響してはいるがあの綺麗な音は再現できなかった。何度か不屈の精神で挑んでは見たが何度やってみても結果はジョボッジョボッでしかなかった。
チルーは水瓶に両手を着いてベンガラ色の内部を覗いた。だが何処にも仕掛けらしき物は見えない。あるのはただベンガラ色の水瓶の色を透けて見せる水瓶の底だけであった。チルーは不思議に思って体を水瓶の淵へ乗せて顔をもっと深く水瓶の内部へ近づけて見た。 水の表面に青空と白い雲と自分の目をまん丸に見開いた目が見えた。 謎を解き明かそうとする懸命な自分の顔が水瓶の水面に映っていた。余りの驚きの自分の表情に思わず可笑しさがこみ上げて声を上げて笑った。その笑い声がベンガラ色の大きな水瓶の内部で反響して妙に甲高く響いて聞こえた。チルーはその音に甲高さがあの琴の雅な調べと似ていると感じた。チルーは遂に謎を解き明かしたようだ。心が小躍りしていた。思わず頭を思い切りもっと深くベンガラの水瓶の中へ押し入れた。 なんとチルーは勢い余って逆さになって水瓶の中へ頭から転落してしまった。幸いに水の量が少なくって溺れるには至らなかったが頭蓋の天辺をしこたまに打った。水が多ければ頭は打たなくて済んだだろうがきっとそのまま溺れ死んだであろう。水瓶の中で頭を下にして足だけが水瓶から生えているように出ていた。 自分の鳴き声が水瓶の内部で渦巻いて反響して響いてくる。その音にますます驚いてしまうチルーだったが自分の憐れな姿が少し滑稽に思えてきた。泣き声が反響して聞こえる不思議な世界がチルーの思わぬ窮地を別の世界へ誘ってくれた。泣き声が突然笑い声に変った。ベンガラ色の水瓶に逆さになって落ちたままの姿でチルーは夢の国の不思議な笑い声にますますのめり込んでいた。
チルーの笑い声はベンガラ色の水瓶の内部で増幅されて奇妙な甲高い笑い声となって松田の屋敷の庭に轟いて聞えた。 機織機がある松田の屋敷の納屋で奉公の女中に機織の糸のかけ方を教えていたチルーの母千代は奇妙な笑い声に気づいて女中と目を見張って驚いた。先に女中が納屋から飛び出してきた。千代は織り糸の束を肩にかけたままで女中の前へ駆けて飛び出した。異変にまず千代は空をぐるりと見回してみたが空はただ澄んでいて真っ青なだけで普段と違う様子は見当たらない。つぎに屋敷の中を見た。屋敷へ入ろうと片足が縁側に掛かった時また奇妙な声。声の方向を見やった。右手の母屋の隅にあるベンガラ色の大水瓶に気が付いた。 仰天動地である。千代は眩暈を覚えた一瞬自分の目を疑った。 あろう事か足が水瓶の上に生え出ている。咄嗟に我が娘のチルーの危機を悟った。 「ウムチルーヨーデージナットォー(思鶴が大変な事になっている。)」と叫んで片足は草履をはずしたままで水瓶に走りよった。水瓶の傍にたった千代は小さな足を両手で掴むや否や空中高くへ持ち挙げた。逆さに引き抜かれたチルーの体が宙で揺れて重たい頭がベンガラ色の水瓶の淵に当たった。「ゴン」と鈍い音が聞えてチルーの目ん玉からいやと言うほどの火花が飛んだ。 チルー打ち付けた部分が痛いと感じたが助かった気持ちが勝って言って泣くほどではなかった。それどころか逆さまのままぶらぶらと揺れてなんだか楽しい気持ちになった。 いつもと逆さまな母の姿もやはりイッペーチュラサンだ。(とても美しい。) チルーのはちきれんばかりの笑顔に安心した母千代はチルーを逆さに持ち上げたままで女中と目を合わせて笑った。その笑い声にチルーはまたまた楽しさが溢れて逆さ吊りのままで満面の笑顔で一緒になって笑っていた。突然笑いの渦が襲って千代は手の力が抜けてチルーを脳天から落としそうになって慌てて地面にゆっくりと下ろした。降ろして千代は無事であった事を喜んでチルーをきつくきつく抱きしめてあげた。チルーもこの時とばかりに母にしがみついて甘えた。母の柔らかな胸がチルーにはなんだか懐かしい感じがした。いつも家にいる母なのにこの頃はめっきりとご無沙汰しているように感じた。 チルーは母の胸の中に顔をうずめてあのベンガラ色の水瓶から聞える水琴窟の琴のような雅な調べが母の内から伝わって聞えてくるように感じて心地のよい気持ちに満喫して母に抱かれたままいつの間にか睡魔に襲われていた。 千代は我が胸に顔をうずめて眠たそうな我が子チルーの寝姿に愛おしさがこみ上げてきた。この所少し忙しさに追われてゆっくりと親子で語り合うことが少なくなっていた。 チルーの柔らかな黒髪を撫でながらその事が申し訳なく思って詫びた。暫くこのままこの胸の中で眠らせて置いてあげようと思いその場に腰を下ろしてチルーの体を深く両腕で包み込んだ。
それは優雅な鳳凰鳥の親鳥が可愛い雛鳥を温かな美しい羽毛で包みこんでいるようなほほえましさと優雅な美しさを松田の屋敷の広い前庭一杯に漂わせて見えた。 琉球の天は本格的な夏に向かって焦げ付くような太陽の光を一団と強めて地上に注ぎ暑さを喜ぶ生き物たちに限りないほどの恩恵を大量に施してくれる。 それまでには暫くは大量の雨が降り注いで生き物たちに十分な水分を補給する時も用意していてくれる。まるで愛情こまやかで温かな親子関係のようにきめ細かく抜かりない至れり尽くせりである。。 だから琉球の民は自然界の神を崇め尊ぶ。 そして敬う。太陽こそ琉球の神々の中心的な存在である所以だ。そしてそれは日本の国も同じである。 琉球と日本は古来より同祖同神。衣食住、習慣すべてが同じであった。勿論文化も言語も全く同一の時期も確かに存在している。ただ悠久の時の流れの中で水琴窟の水滴が造る波紋の広がりのようにうねりが中心と外側とを多少伸び縮みさせて差異を感じさせているだけである。下地にある水は元来本質であり変りようがない事実である。それを無理に切り離して検証し様とする事事態がおろかしい事だ。 私は子供の頃から半世紀この問題を考えている。 |
[*註1:「」:。]
|
第十一話「翔と翼」ふたりの大好きなチルー!」につづく
|
[崋山仁愛:作者へメールする!]
|
|


 そうでなければ余りに不憫で不公平な運命の悪戯だ。(なぜこんな優しい心の天使のような女の子が不幸なままでその短い人生を遂えなければいけないのだろう。アンマーハ祈れるものであればなんにでも祈っていた。願いを聞きとめてくれる神があれば願いを聞きとめてくれるのが神でなくてもたとえ悪魔であったとしてもなんでもいいからチルーをあの世へは生かせないでくださいと自分のこれまでの人生の中でこんなにも憐れに悲痛な叫び声で神や仏すがったことなどなかった。替れるのであればその自分の身を地獄に落とされてもかまわないからチルーだけは連れて行かないでください。アンマーは悲しみで気が狂わんばかりに泣いた。涙が熱くアンマーの鼻頭に伝って糸を引きながらポタポタと零れた。あの気位の高い吉屋の看板女将が、非常と言われ無情と言われて後ろ指を差されて蔑まれていたあの女将が泣いた。
そうでなければ余りに不憫で不公平な運命の悪戯だ。(なぜこんな優しい心の天使のような女の子が不幸なままでその短い人生を遂えなければいけないのだろう。アンマーハ祈れるものであればなんにでも祈っていた。願いを聞きとめてくれる神があれば願いを聞きとめてくれるのが神でなくてもたとえ悪魔であったとしてもなんでもいいからチルーをあの世へは生かせないでくださいと自分のこれまでの人生の中でこんなにも憐れに悲痛な叫び声で神や仏すがったことなどなかった。替れるのであればその自分の身を地獄に落とされてもかまわないからチルーだけは連れて行かないでください。アンマーは悲しみで気が狂わんばかりに泣いた。涙が熱くアンマーの鼻頭に伝って糸を引きながらポタポタと零れた。あの気位の高い吉屋の看板女将が、非常と言われ無情と言われて後ろ指を差されて蔑まれていたあの女将が泣いた。  茜の空が満点を尽くして青い海まで金紗に染めて輝いていた。(そんな雄大な夕焼け空を遊郭の吉屋の二階の窓辺に腰掛けて京の都の打ち羽で涼風を美しい頬に扇ぎながらチルーは遠い故郷おとぅとおかぁを思い出していた。 母父はゆかてぃ うまり島ぬいみぃて 我が身や仲島ぬ ついにかえれなく(つぃんいじゃら) 「おとうもおかぁもも故郷でげんきにしているだろうか。私はこんなところにいてまるで籾殻の様なものだけれど元気にしてますよ。まだ一度も帰ってもていないけれど。みんなはどうしているだろうか」と郷愁に胸を焦がしながら茜にに染まる夕暮れに遠く浮かぶ慶良間の島影を眺めていた。 三日三晩がそうして過ぎていった。その間いだ中女将が他の者に手配させた凄腕の霊力を佩びた王府から高位を得て実権を持ったその時代最高の祈祷師ユタ神を何人も楼へ呼び寄せて不眠不休の祈祷をさせた。なんとしても死なせないで下さいと何度も何度も女将はユタ達に泣き縋って懇願した。 京の都の雅やかさを随所に鏤めた紅型染めの煌びやかさに似た吉屋楼閣の佇まいはその時ばかりは色あせた廃屋のように世間から忘れられて捨てられて往くような侘しさと酷さが精緻な織物のように縦横に綾なして見えていわれなく哀愁を漂わせて時の流れだけが虚しく大河の瀬々らぎの様な静寂の流れを創り出して無常にも刻んで過ぎてゆく。
茜の空が満点を尽くして青い海まで金紗に染めて輝いていた。(そんな雄大な夕焼け空を遊郭の吉屋の二階の窓辺に腰掛けて京の都の打ち羽で涼風を美しい頬に扇ぎながらチルーは遠い故郷おとぅとおかぁを思い出していた。 母父はゆかてぃ うまり島ぬいみぃて 我が身や仲島ぬ ついにかえれなく(つぃんいじゃら) 「おとうもおかぁもも故郷でげんきにしているだろうか。私はこんなところにいてまるで籾殻の様なものだけれど元気にしてますよ。まだ一度も帰ってもていないけれど。みんなはどうしているだろうか」と郷愁に胸を焦がしながら茜にに染まる夕暮れに遠く浮かぶ慶良間の島影を眺めていた。 三日三晩がそうして過ぎていった。その間いだ中女将が他の者に手配させた凄腕の霊力を佩びた王府から高位を得て実権を持ったその時代最高の祈祷師ユタ神を何人も楼へ呼び寄せて不眠不休の祈祷をさせた。なんとしても死なせないで下さいと何度も何度も女将はユタ達に泣き縋って懇願した。 京の都の雅やかさを随所に鏤めた紅型染めの煌びやかさに似た吉屋楼閣の佇まいはその時ばかりは色あせた廃屋のように世間から忘れられて捨てられて往くような侘しさと酷さが精緻な織物のように縦横に綾なして見えていわれなく哀愁を漂わせて時の流れだけが虚しく大河の瀬々らぎの様な静寂の流れを創り出して無常にも刻んで過ぎてゆく。  誰もが一様に天に助命の懇願を祈り地に臥してさめざめと泣いていた。かってこの世にこれ以上の悲しみなどこの麗しの島琉球には存在しなかったかのように。まさしくどこを探しどの地を掘り下げていったとしても金輪際探せ出せはしないような一大事に思えてチルーの生涯に憐れを募らせずにはいられない者ばかりで吉屋の楼閣の座敷が悲しみに打ちひさぐ者達で溢れていた。集まった者万余を越える如く中庭を埋め尽くし楼外を処狭しと取り巻いてチルーの息が再び漲り始める事を望んで朗報が今や遅しと待ち焦がれていた。探し出せはしない。
誰もが一様に天に助命の懇願を祈り地に臥してさめざめと泣いていた。かってこの世にこれ以上の悲しみなどこの麗しの島琉球には存在しなかったかのように。まさしくどこを探しどの地を掘り下げていったとしても金輪際探せ出せはしないような一大事に思えてチルーの生涯に憐れを募らせずにはいられない者ばかりで吉屋の楼閣の座敷が悲しみに打ちひさぐ者達で溢れていた。集まった者万余を越える如く中庭を埋め尽くし楼外を処狭しと取り巻いてチルーの息が再び漲り始める事を望んで朗報が今や遅しと待ち焦がれていた。探し出せはしない。  万余の人々の願いと女将の悲痛な叫びが天の心に響いて黄泉の河辺で対岸を見つめて佇む憐れなチルーの耳に達したかのように突然の如くチルーの美しい瞳は微かな輝きを取り戻し始めていた。もうどうにも止まらない!(リンダ風)味わってください。崋山仁 愛
万余の人々の願いと女将の悲痛な叫びが天の心に響いて黄泉の河辺で対岸を見つめて佇む憐れなチルーの耳に達したかのように突然の如くチルーの美しい瞳は微かな輝きを取り戻し始めていた。もうどうにも止まらない!(リンダ風)味わってください。崋山仁 愛







 日本が向かうところは・・・
日本が向かうところは・・・






























































 吉やチルー&恩納ナビー 琉球女流歌人双璧の対比を考察する。|
吉やチルー&恩納ナビー 琉球女流歌人双璧の対比を考察する。|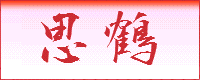

 源為朝の伝説の真実は如何に!」
源為朝の伝説の真実は如何に!」



 so-net blog
so-net blog




